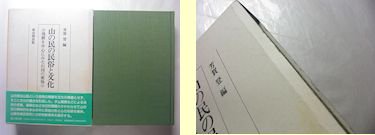
1991年 A5判 P527 帯背少シミ汚れ、僅ヤケ 函シミ汚れ、背ヤケ、端イタミ 本体裏遊び紙僅値段消し跡
“山の民は山岳という自然の障壁を文化の障壁とせず、そこに文化の接点を形成した。ダム開発などによる自然の変貌、過疎化など今日的課題とかかわらせて山の民の開明的な歩みの中に民俗の形と心の存続を模索。山国地域史研究に分析的新視覚を提示する。”(帯文)
目次:
まえがき
第一章 山国地域史研究の一視角
Ⅰ 山国飛騨の人と民俗(芳賀登)
{はじめに/山国飛騨の民俗的特徴/山国飛騨と「山の民」/『斐太後風土記』編纂と富田礼彦}
Ⅱ 飛騨山脈と日本の東西文化(芳賀登)
{飛騨山脈と「山の民」のくらし/江馬修の小説『山の民』/飛騨近現代史の課題/東西文化と飛騨山脈との関係/今後の課題}
第二章 近代における飛騨高山の発展
Ⅰ 鉄道敷設運動とくらしの変化(芳賀登)
{飛騨の主都・高山の誇り/飛騨縦貫鉄道敷設運動と飛騨高山/乗鞍開発・北アルプス開発と飛騨高山の観光化/高山市の町家の役割とその方向}
Ⅱ 伝統の保存と近代化(芳賀登)
{町家の保存修景/近代化と山都高山/奥飛騨温泉化と近代化}
第三章 人口と地誌
Ⅰ 人口と食糧問題(坪内庄次)
{飛騨の米穀精算とその南北流通の地域構造/飛騨の飛・信間東西交通の軸としての野麦街道/奥山中地域の人口と食糧生産}
Ⅱ 飛騨国人口論と大家族制度(芳賀登)
{飛騨国人口論と白川村大家族制度/飛騨社会の特徴と白川村大家族制度}
Ⅲ 『斐太後風土記』にみる飛騨の食糧(江原絢子)
{はじめに/『斐太後風土記』の背景/『斐太後風土記』刊本と写本の関係/飛騨の主な産物と流通/他国から飛騨に買入れた必要品/飛騨の村の主食物/飛騨の村のくらし/主食物と村のくらしの関係/高山の町のくらし/行商と出稼/おわりに}
第四章 宗教と儀礼
Ⅰ 飛騨・加賀の白山信仰(阿部肇一)
{泰澄大師と白山開山伝説/泰澄信仰と白山神への同化/神仏習合化過程/泰澄の山岳修業と白山信仰}
Ⅱ 飛騨地方の信仰と仏教(阿部肇一)
{白山信仰/白山信仰と飛騨の仏教/真宗の活動/禅宗の活動(臨済宗)/禅宗の活動(曹洞宗)/在俗信者の活動/むすび}
Ⅲ 益田郡中呂の大前家の儀礼食(江原絢子)
{はじめに/中呂村と大前家/婚礼の献立/仏事の献立構成/階級による献立/饗応材料とその調達/おわりに}
第五章 政治・国境・交通
Ⅰ 道を中心とした飛騨の政治(後藤新八郎)
{はじめに/飛騨の政治(太古 古墳時代 奈良時代 平安時代 鎌倉時代 建武中興・室町時代 戦国時代 金森氏領国時代 代官時代 明治維新 近代現代}
Ⅱ 東西境界地域の国境(谷口研語)
{はじめに/境界領域としての木曽/境界地域におけるその他の事例/おわりに}
Ⅲ むかしの飛騨の交通と産業(井原政淳)
{問題の視点/「交通」の東西社会におよぼした影響/「産業・流通過程」の東西社会におよぼした影響/むすびにかえて}
第六章 産業の近代化
Ⅰ 明治二~四年ごろの飛騨のの養蚕業(安藤萬壽男)
Ⅱ 飛騨と信州の産業基盤の比較(安藤萬壽男)
Ⅲ 三井組による神岡鉱山の統合と技術者集団(岩崎宏之)
{はじめに/明治初年の神岡諸鉱山と三井組/明治十九年、三井による神岡全山の統合/神岡全山統合の技術的側面}
第七章 学区・学制の展開と洋学導入
Ⅰ 学制期における地方教育行政―筑摩県飛騨地方を中心として(磯辺武雄)
{はじめに/学区取締の任命/学区取締の職務/学区取締の教育行政上の地位/学校世話役の存在と役割/学校主管入/おわり}
Ⅱ 維新期における洋学教育の導入―加賀・飛騨を中心に(鈴木健一)
{はじめに/加賀における洋学教育/飛騨における状況/おわりに}
Ⅲ 飛騨高山の幕末・明治初期の学校(井原政純)
{はじめに/赤田教授所の“郷校”としての性格/明治初年ごろの静修書院と梅村知事の“学校所”計画について/“思誠館”についての一考察/煥章学校に関する三資料の考察/むすびにかえて}
第八章 観光の飛騨高山と奥飛騨温泉郷の形成
Ⅰ 飛騨開発と人々のくらし(芳賀登)
{はじめに/「飛騨高山」の観光都市化/野麦峠と平湯・安房峠/奥飛騨温泉郷の形成/飛騨山脈(北アルプス)登山}
Ⅱ 山国飛騨の今後(芳賀登)
{飛騨開発と保存の現代的課題/現代の高山観光の課題}
あとがき
執筆者のプロフィール